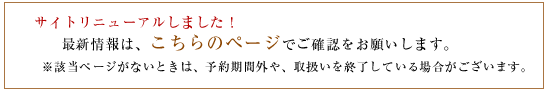山形の谷沢梅(梅干用の梅)通販・販売
大粒の梅にはない味わいと使い勝手のよさ。
そして実離れがいい。梅干しに最適な梅「谷沢梅」。
山形県寒河江市にある「谷沢」という小さな集落で古くから(400年とも)守られている在来種の梅があります。その地名をとり「谷沢梅(やさわうめ)」と名付けられています。やや小振りながらも、梅干しにすると「果肉と種がすっと離れる」ので食べやすく、地元の人に親しまれてきました。
戦後には、この梅をばっちゃんたちが漬けては、遠くは仙台まで行商をして人気が高まり、一時は増産されましたが、さくらんぼの雨よけ栽培が普及すると収穫時期が重なり、作り手は減少。さらに高齢化も進み、今では作り手はわずかとなった貴重な梅です。
ここ数年、谷沢梅生産組合様の活動によって、その価値が内外から評価され、ブランド化の動き(品質向上・キャラクター「谷沢梅左衛門」・認証マーク)も出てきました。
梅干しにすると実離れがよく、滋味深い味わい。
梅干用においしい小粒〜中粒の梅「谷沢梅」です。
我が家では、大粒の南高梅しか漬けたことがなく、山形に移り住んだ2006年に、運よく作り手に出会うことができ、谷沢梅をいただき、興味本位、疑心暗鬼な気持ちで作ってみました。
地元に伝わる谷沢梅の漬け方
農家の方が漬け方のコツを教えてくれました。この地方で代々作られてきた方法があり「夜露にあてながら三日三晩、外で干し続け、一度梅酢に戻し、もう一度この天日干しを行う」そうです。
その後、話しをしてくれた谷沢梅生産者はみな、これを口にします。夜温の低い山形の気候風土に培われた「地元の人々が口伝えで伝えてきた伝統製法」です。
干し上がった梅干しは、とても滋味深い味わい。言われている通りに実離れもよい。紫蘇の色づきもよくきれいな色に仕上がりに。お弁当やおにぎりにもちょうどよいサイズで使い勝手も抜群。一樽にたくさん漬け込むことができ、これは家庭用にぴったりだと思いました。
梅自体の仕上がりが年によって異なりますが(半夏から10日あたりのものがよいとされる)、漬け方、干し方でずいぶんと味が変わるものです。
真夏になり1週間ほど干せば、まるでねり梅のような濃厚な味わいになり、まったく干さなくてもとろりとした仕上がりの梅干しも楽しめます。通常通りに漬けたものでも、3年、5年、10年と経つと食べるのはもったいない、売っていたら一粒いくらだろうか、と思えるような絶品の梅干しになっています。

なにしろ、一年間、おいしい梅干しが楽しめて、春夏秋冬、私たちの体を整えてくれるのです。だから梅干し作りはやめられず、この梅がなくなてはならないのです。
はじめての方でも簡単。お試しに2.5kgほど漬けてみませんか。
「珍しさ」ではなく、「おいしさ」で「じわりじわり」とファンが増えています。毎年梅干作りを楽しまれている方にとっては、この幻の梅をコレクション?の一つにしてみてはいかがでしょうか。


MとLLのサイズ比較
写真右の手前がM玉(直径27mm未満/9g前後)、L玉 は直径30mm未満、2L玉は33mm未満/18g前後(谷沢梅の規格・谷沢梅生産組合)。販売単位:5kg箱のものを再選別して鮮度保持袋に小分けし、2.5kg、5kgの単位で販売しています。
谷沢梅はこちらからご購入いただけます(ご予約:6月中旬まで)
楽しい梅干作り



我が家の梅干しの塩加減は、カビを恐れて梅の重量に対して18%の塩(地元では14%が主流)。これで昔懐かしい、自然と共存できる、日本人が食してきた梅干しの味わいとなります。
毎年、梅の熟度や紫蘇の量、干し具合(天候)でいろんな仕上がりを見せる梅干しは、どれも愛らしくとてもおいしい。写真で色の違いは、完熟したものとまだ完熟していない青いものが混ざっているから。どちらも捨てがたい味なのでわけずに漬けています(仕上がりを合わせるためには、漬け込む時点で、梅を色で選別します)。
梅干は、月日を重ねてじんわりと熟成していく味を楽しめるのもまた楽しみ。とくに「谷沢梅」は2年、3年目と一段とおいしくなっていくような気がします。梅干作りと自家製の安心な梅干しのある豊かな暮らしが健康を支えてくれています。
はじめての方の梅干し作り
★塩の量:梅の重量に対して18%(食塩濃度は15%)
はじめての方はこの塩分で。失敗が少なく、長期保存を可能にする塩分です。谷沢地区の梅干しは13%。
★塩は、天日塩・甘塩がおすすめ
塩がおいしければ、塩の感じ方も異なり、梅干しはおいしく、ミネラル分も豊富になります。自家製だからこそ、精製塩を使わずに作りたいものです。ちなみに精製塩の塩化ナトリウムは99.9%、伯方の塩は95.2%、赤穂の塩は92%。岩塩は、マグネシウムを含まず、溶けにくいのでおすすめできません。
※漬け込む前に梅の量を再計量し(はじいた分などがあるため)、塩の量を求めてください。
※この塩分だと常温・長期保管が可能です。まずはこの塩分で失敗のない梅干し作りを経験して、減塩梅干し作りへ。
★梅干しの漬物樽のサイズ:5kgなら15型(トンボ規格)
保管場所の兼ね合いもありますが大は小を兼ねます。高さがあるより薄くならべたほうが水のあがりもよいのです。漬物用の袋もありますのでひと回り大きいサイズをご用意してください。
★重石:梅と同量の重石を二つ(5kgなら5kg×2個)
水があがるまで(3〜4日)二つ。水があがったら一つに。
※梅の熟度で重石を加減する(完熟の場合は軽くする・底には青、上は黄色など)。
※水を入れたペットボトルなどで調整も可能。
※1〜2日ほどが経ち、水があがりはじめたら、それを呼び水として樽ごとゆっくり廻してなじませるとさらに水の上がりが早くなります。
はじめての梅干し作り 下処理篇
梅は一つ一つ丁寧に扱うとその後の傷みも少なくなります。
梅は完熟すると黄色くなります。その一歩手前がベストです。
梅の到着後に・・・袋から取り出して傷んでいるものはすぐに取り除き、常温で1〜2日ほど追熟させます。梅がやや黄色くなると香りもよく梅酢があがりやすくなります(追熟後に傷みや皮に茶色いシミのあるもの、色が変わらないものは取り除きます)。熟度が過ぎると皮がやぶれやすくなりますので、全体の8割ほどを目安に(黄色くなってきたな、香りもよくなってきたな、まだ少し青いところもあるかな)追熟を終了して漬け込みます。
※カリカリ感を残すために追熟させないでそのまま漬けられる方もいます。
※追熟がほかより遅い青い梅は、実や皮が硬ったり、紫蘇の色が入りずらいので、待たずに別に利用したほうがよいです。少量でも開いた小瓶などを利用して「梅酒」、砂糖漬けにする「梅酵素液」、「醤油漬け」「味噌漬け」「味醂漬け」や「お酢漬け」も簡単で食卓を楽しくする飲料や調味料となります。傷んだ梅も黒ずんだ部分をカットし同様につけられます。
谷沢地区では、「昔から青梅は細かく刻んで塩で揉み(揉み紫蘇があれば加えて)、カリカリ梅を作り、それをごはんに混ぜておにぎりにしてよく食べた」という情報も。夏仕事を乗り切る力飯ですね。お試しください。


1. 届いた梅を常温に戻し選別して追熟させます。追熟の目安はこれより青い状態。これはやや過熟の見本。

2. ヘタを爪楊枝などで取り除きます。

3. 梅を樽に入れて水に30分ほど漬けておき、梅同士を軽くこすりつけるように水洗いします。
※青い物はアクを抜くために一晩ほど水に漬ける。水に漬け過ぎは腐敗、カビの原因に。
4. キッチンペーパーなどでよく水気をふき取り乾燥させます(重要)。
※日干しは傷むので陰干しに。
5. カビ対策として焼酎を霧吹きで吹きかける。
これで下ごしらえ終了です。
漬け方の手順
- 漬物用のビニールを漬物樽に入れる。
- 底に塩をして、梅を一段ずつ並べて、塩を振る(一回に一掴み弱・残量を見ながら)、を繰り返す。
※最後に塩を多めにかけたいので、一掴み程度を別にとっておく。 - 梅の上に中蓋をのせ、その上に重石をのせる。
- 焼酎を霧吹きで吹きかけてから密封します。
※ビニールを使わない場合は重石ごとラップで包む。

- 梅酢があがり土用干しするまでカビが生えなければ、ほぼ成功です。
- 紫蘇を手に入れたら・・・ボールに塩をたっぷり入れて、パン生地をこねるようによく揉む→アク(泡)が出てくるのでそれを搾って捨てるという工程を3度ほど行い、梅と一緒に漬け込む。すでに加工された揉み紫蘇もあります。
- 土用干し・・・晴天が続く日を狙って三日三晩。梅を揉みながら天地返しをする。
※皮がやぶれてしまったものは、その場で取り除き、食べてしまいます(食べられます)。 - 一度梅酢に戻し、もう一度天気の良い日に天日干し。
※紫蘇は梅干し瓶詰後の蓋変わりにのせます。
※カラカラになるまで干せば「ゆかり」に。
※梅を干す理由・・・皮がやわらかくなる、乾燥させて保存しやすくなる、赤梅酢に戻せば色づきもよくなるなど。
※「土用干しは梅雨明けの~」にこだわらずに、晴天が続く日であればいつでもいいと思います。
※干した梅をまた梅酢に戻してそのまま保管している方もいます。
- 保存瓶に詰め替えて終了!
※梅酢は保存ビンに入れて。紅生姜作りや料理の隠し味、夏場の栄養ドリンクに。
~ある年の谷沢梅の梅干し作り失敗談~
よい香がします(3日ほど)。これに気をよくしてもうちょっと追熟させてみました。これは危険な行為です。
| ヘタを取ったらアク抜きのため水に漬けます。美しい。 | このくらいはロスが出ます。デリケートな梅は仕方ありません。この黒い部分をカットして、小瓶で醤油漬け、味噌漬け、酢漬けなどを作って。 |
| 均一に圧がかかるようヘタを下にして。 | さくらんぼの手詰めの感覚のようです。 |
| この調子で上段まで。残った青いものは梅酒へ。 | 水があがりました。やはりいい状態。フルーティーでいい仕上がりに期待と思いつつ、 |
| やわらかくなりすぎました。そっとさわらないと、、、 | 底のほうには破れているものもあり、、、 |
その皮が破れたものを食べると・・・とってもおいしい!
それに、これを干したら、天地返しするたびに皮が破けたりするんだろうな、と
このままそっと瓶詰めすることに。
半年後、熟成しました。とろりとしてフルーティー。これはこれでよし。干していないので梅漬けです。カビの発生がなく、味だけはよいことが救いでした。
ほかに、梅の重量に対して塩を18%にしても、カビが生えることがありますし、先に梅を計量してしまい実際に漬け込む量が減ったため、塩気が強すぎるなどの失敗もあります。梅を丁寧に扱い、基本に忠実に作業することの大切さを教えてくれました。
梅は黄色くなってから漬ける?追熟させても青い?
梅干しづくりでは、手に入れた梅が青い場合や青味がかっている場合は、常温にさらして自然に実をやわらかくさせるために「追熟」をさせます。追熟の判断は「香りがよく黄色くなったら」というもの。「黄色く追熟させてから」の判断は難しいものです。
谷沢梅は流通時間を考慮して黄色く熟したものは出荷しません。このことは共通ですが、毎年同じ梅を使ってきてわかったこととして、追熟の度合いは「その年の気象条件」「収穫時期の条件」によって変わること。同じ大きさで同じ程度の色をしていも、追熟の程度に個体差があります(生産者も見極め難)。
青いままの梅は未熟(カリカリ小梅や梅酒などに使われる青梅の状態)と判断し、追熟を期待せずに、醤油やお酢、味噌などお好みの調味料とともに小瓶に漬け込んで梅の香りのする調味料にすると無駄とならずにおいしいものが増えることになります(黒ずんだ梅も同様です)。
※未熟で青い梅を漬けてみると、写真の左のような仕上がりになり、硬くておいしくありません。

青梅の活用・・・
・小粒の谷沢梅を青いまま漬けると山形の昔ながらの梅干しができます。
・谷沢地区では、「昔から青梅は細かく刻んで塩で揉み(揉み紫蘇があれば加えて)、カリカリ梅のようなものを作り、それをごはんに混ぜておにぎりにしてよく食べた、これで暑い夏も力が沸いてよく稼げた」そうです。夏仕事を乗り切る力飯ですね。簡単で少量でもできるので青梅が混ざっていたらお試しください。